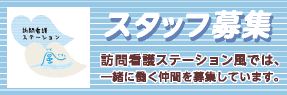2025年 新年のご挨拶 『小さな世界』 1月7日 土屋秀則
昨年のこと、私が担当している利用者さんがこう言ったのです。「土屋さん、ギターでもピアノでもサクソホーンでも何か楽器を買って、それを叩いたら、もうそれで土屋さんは音楽家なんですよ」と。
この言葉は、高度な技術というものに対するアンチテーゼとして発せられたものではなく、彼が本当にそう思って私に伝えたのです。
私にとって利用者さんが言ったことは本当でした。上手くはないですが、今、私は幸せなことに私の小さな世界で音楽家をやっています。
利用者さんが言ったことは、音楽に関したことだけではなく、生き方や考え方にも通じるものがあると思います。
人は、それぞれ、何か叩くものを持っていると思います。それは、楽器ということもあると思いますが、鍬だったり、針だったりする場合もあるでしょう。眼だったり手だったりすることもあると思います。口だったり声だったり、お尻だったりする場合もあるかもしれません。そして、仕事だったりすることもないとは言えないのでは、と思います。
私は、日々星を見るように多くの利用者さんと利用者さんに起きることを見ています。これは、小さな世界でありシンプルな生活です。
利用者さんのように考えられるのは、利用者さんや私が生きているような小さな世界に限ったことなのでしょうか。
実は、若い日の私はもっとシンプルでもっと小さな生活を望み、そのように生きていました。そこでの私は、少ししか魚が取れなくても漁師であり、小っちゃな家しか建てられなくても大工であり、虫に葉を食べられてばかりいても農夫でした。夜は満天の星を眺めていました。
今も昔も私は、小さな世界で生きることは幸せへの近道なんだ、という実感があります。
ひるがえって世の中を見れば、人も社会もそのような在り方はしていません。お金や優位性や支配力を求めることだけに人が動き回っている姿が見えます。幸福は個人のものとして過剰に求められ、愛も個人のものとして子や家族に過剰に注がれています。競い合いを超えて奪い合いのような情勢です。元来、人とはそういうものなのでしょうか。
人間が人間となった頃も、もちろんそういった傾向はあったかもしれません。しかし、現代のようではなかったと思います。山際寿一の論文やコンゴの森林奥に住む部族のドキュメンタリーを観てそう思いました。集団外の人間に対しての警戒心はあったかもしれませんが、集団内においては対等性・平等性が現代よりずっと重んじられていたようです。行き過ぎた利己的な競い合いが創り出した現代の格差や抑圧、支配はなかったと推測します。
生前に、少しお付き合いをさせてもらった詩人がいます。彼の詩に、「人は、火を焚けたらそれでもう人間なのだ」という一節があります。私は、この言葉と、私の利用者さんの言葉が、同じことを言っているように聞こえます。
障害のある人も、自分には障害はないと思っている人も、人は様々な思想を持ちながら生きています。人が1億いるとして、実際思想は幾つあるでしょう。2つなのか10個なのか、1億なのかは分かりません。ただ私はこれまでの人生で、小さく生きるという思想を持っている人に何人か出会いました。そして昨年、こんなにも身近に、仕事の中で、若い日に私が求めた思想を利用者さんから聞くとは思いませんでした。幸せな事です。
現代社会は大きすぎる世界です。
私は、小さな世界で生きている人たちの中には、色々な面で行き過ぎてしまった大きな世界に対するクールで且つ温かいメッセージを持っている人が少なからずいると思います。
それが少しでも伝わっていけばいい、と願わずにはいられません。
今年もよろしくお願いします。