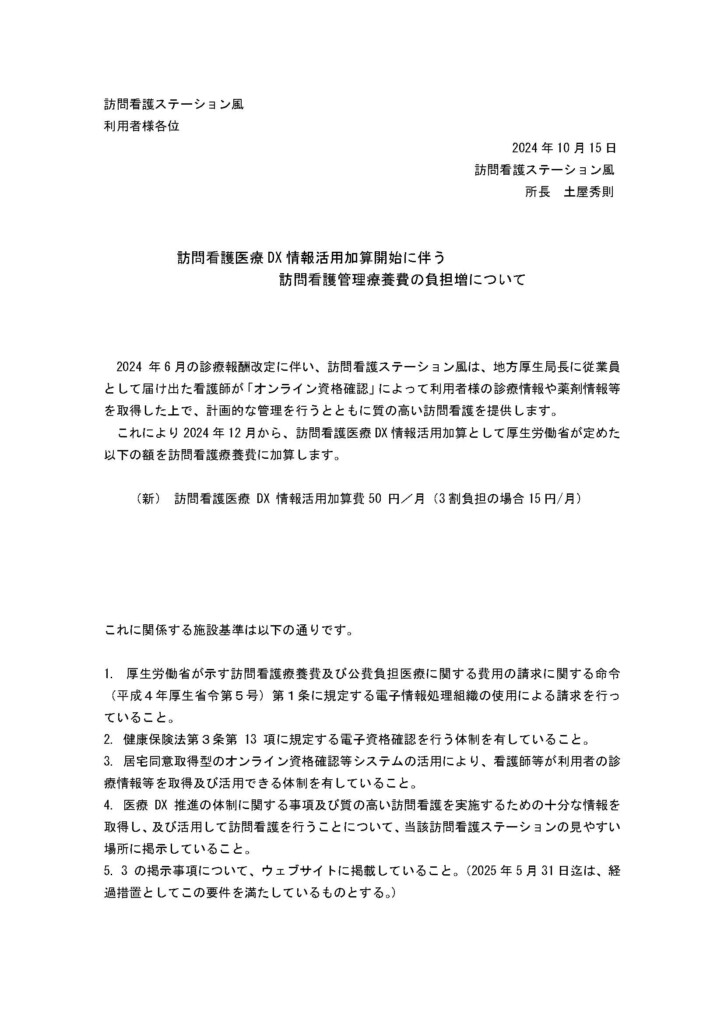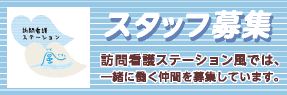訪問看護ステーション風
土屋秀則
〈はじめに〉
「対位法的訪問看護-試論-」は、音楽理論の“対位法”にヒントを得て考え出され名付けられた理論である。
人間の集団には、所属する人それぞれの考え方が違っていても、調和がとれた良好な人間関係が成り立っている場合がある。その在り方は、対位法音楽によく似ている。
訪問看護においても対位法的な関わりを持つことで、集団や所属する個人への支援の効果を上げることが出来るはずだと私は考えた。訪問看護が、利用者に対してのみ支援を行なうものではなく、その家族や他の支援者たちと長い時間を共有しコミュニケーションを取りながら関係者全体を支援しているものだからである。
※「対位法」については文末に記した。
A 概論
この試論は、利用者のみならず、利用者の家族、就労支援事業所のメンバーや職員他、様々な支援者の感性や考え方を最大限尊重し合う関係性を作ることで、個々の関係性が肯定的な関係性に変わり、関係者全体の精神に調和が生まれ、利用者自身の回復にも効果がおよぶことを目指す考え方である。
“風”の支援は、この「対位法的訪問看護-試論-」(以下「対位法的訪問看護理論」と書く)に基づいて行なっている。
1、支援の目標
対位法的訪問看護理論を用いた支援の目標は、利用者はじめ利用者が所属する家族等の集団内の一人ひとりまた多くの支援者との間にある関係性全体に調和が生まれることである。利用者のみが回復し成長していくということには置いていない。
2、支援の焦点
対位法的訪問看護理論を用いた支援の焦点は、利用者個人の“精神”ではない。それは、精神科訪問看護においては、利用者の対人関係で生じる問題に関わることが第一義的な仕事となっているからである。
利用者の自立のためのグループホーム入居を巡り、利用者と両親の考えが合わず、利用者の症状も悪化してしまうという例で考えてみよう。
このようなとき、利用者の気持ちを分析し正しいと思われる解決策を提示しても、それが役に立つというようなことは余りない。一方で、両親の気持ちを分析し両親に何らかの提案をしてみても矢張り同じである。双方の間に入って何らかの折衷案や約束事を決めても、症状が悪くなるばかりで元も子もなくなる。
良かれと思う考えを提示してもその通りには行かないものである。私たちは、上記のような関わりを行なって何十年にわたって失敗し続けて来たような気がする。
訪問看護を行なってすぐのこと私は、利用者個人や家族のような集団のメンバー一人ひとりに関わるよりも、利用者に関係する人たちの対人関係全体の“精神”に関わることの方がよほど大切なことに気が付いた。
対位法的訪問看護理論の焦点は、利用者が所属する集団また関係者との間に存在する関係性の中にある精神である。
3、対象と場面
対位法的訪問看護理論は対象と場面を選ばない。どのような対象や場面であっても、対位法的な対人関係を目指すこの理論は私たちの基本的な立ち位置である。
精神科訪問看護の利用者は、統合失調症や気分障害、発達障害、知的障害、認知症まで様々な症状と障害を持った人たちである。多くの利用者は、疾患が重複し、感性や考え方は千差万別である。また、その家族や支援者も同様である。だからこそ、対位法的訪問看護理論を用いて集団に調和が生じるよう働きかけるのである。
例えば、入院の必要性が生じた利用者がいるとしよう。
対位法的訪問看護理論は、入院時の支援としても用いることが出来る。例え強制的入院となったとしても、医師の判断だけではなく、入院の瞬間まで本人の意思も家族や支援者の考えも最大限尊重されなければならない。緊急を要する状況でこそ、対位法的訪問看護理論の考え方は基本的支援指針として大切にする必要がある。そのことで、利用者が人を信頼する力を失うことなく、退院後再び家族や支援者の元に戻っていくことが出来ると考える。
B 方法
1、利用者を変えようとしない
私たちの支援は、「どう考え、どのようにしたらいいのか」と悩んでいる利用者(ないしは家族)に対して、利用者(ないしは家族)がストレスなく考え、行動できるようになることを目指すことにある。
ところがこれが簡単ではない。
利用者の考えや行動は、多くの場合対人関係からの影響を受けている。それゆえ支援は、利用者が所属する集団の対人関係全体について考えることなしには成り立たない。
このとき支援は、利用者に対してのみではなく、家族に対してもまた属する集団に対しても、その考えを変えようとして関わることはない。本人を含めた関係者全体に生じている関係性に焦点を当てて、関係性が回復し成長することに注意を傾けて行なう。
症状は改善されないこともあるかもしれない。しかし私は、そうだとしても症状が本人や本人を取り巻く環境と調和出来ていればそれでよいと考える。もし考えが歪んでいようと、少々混乱が見られていてもいい。症状があっても考えが歪んでいても、もし全体として集団が調和に近づいていれば、それは素晴らしい歩みだと考える。
変えようとせず、変わることを期待する、これが基本である。
2、他の支援との関係
私たちはこのように一見消極的と思える関わりを行なうが、他の支援者はそのようには関わらないかもしれない。利用者はカウンセリングを受けるかもしれないし、作業所の職員に相談するかもしれない。
対位法的訪問看護理論は、SSTやCBTのようなセラピーではない。焦点とする処も異なっている。しかし、それらのセラピーと相反するものではない。訪問看護が、セラピーを更に有効なものとする関りを行なうこともあるかも知れない。ただ、セラピーと相反するものであってもいい。異なった立場と考えで関わる、その構成と関係性があってこそ、もし関係性全体に調和が生まれるとしたらそこに深い意味が生じる。
また、対位法的訪問看護理論は、決して“セラピーはセラピー、訪問看護は訪問看護”という離れた支援方法ではない。そのことは大切なことであると考えている。
C 効果
対位法的訪問看護理論の考え方を用いて支援を行なったことでの効果を検証することは出来ていない。
ただ長い時間を掛けてこの考え方を用いて関わった個々の事例をみると、明らかに本人にも家族にも変化が表れ、まるで違う家族のようにお互いを尊重し合うようになり、その関係性が続くという例を見ることは多い。
〈おわりに〉
この試論は、看護学生が精神科訪問看護の理念と方法を理解する上で、多少なりとも役に立つのではないかと考え書いたものである。
学生には、精神科訪問看護がどのような考えのもとに行われているのかの見えにくい処があったと思う。また、指導する当方としても、目で見えない処に焦点を当てている支援は教えづらい処があった。
また、学生が理解しづらい原因として、長い時間の経過の中で行われる精神科訪問看護の極めて短い時間しか学生に体験してもらうことが出来ないという事情もある。そして、そもそも精神科訪問看護を行なうに当たって使用する理論がごく限られていることも影響していると思う。
この試論が、看護学生や他の支援者の日々の実践において幾らかでも参考になることを願う。
※「対位法」は、ウィキペデアに以下のように記述されている。
「対位法とは、音楽理論のひとつであり、複数の旋律をそれぞれの独立性を保ちつつ互いによく調和させて重ね合わせる技法である。
対位法と並び、西洋音楽の音楽理論の根幹をなすものとして和声法がある。和声法が主として、楽曲に使われている個々の和音の類別や、複数の和音をいかに経時的に連結するか(和音進行)を問題にするのに対し、対位法は主に複数の旋律をいかに同時的に重ねるかという観点から論じられる。
J.S.バッハの対位法による作品は、それまでの対位法の集大成といえる音楽である。古典派やそれに続くロマン派の時代では、一つの旋律に和声的な伴奏が付随する音楽が支配的となった」