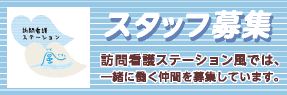2024年 新春に思うこと 『誰も言わない』
2024年1月21日 NPO法人コットンハウス、フレンズ 土屋秀則
元日、大きな地震が起きました。亡くなられた方たちのことを思うと言葉を失います。また、あれから半月以上経つ今も大変な思いをしている方たちが多くいることにも心が痛みます。そのような中でも、多くの人たちが力を出し合って生き抜こうとしている姿や寒さもいとわず支援に入っている人たちの姿を見ると、逆に心が勇気づけられもします。頑張って欲しいと願わずにはいられません。
さて、昨年最も明るいニュースとしてTV各局が取り上げていたのは、大谷翔平選手の活躍のことでした。私も昨年は、土曜日の朝など、大谷選手の活躍が見たくてNHK-BSをよく見ました。大谷選手の活躍は、二刀流という稀な才能だけはなく、その純粋な人間性もあって、なにかとても美しいものを見ているような感動がありました。
その大谷選手のドジャース入団が、昨年12月、1,015億円/10年の契約金で決まりました。その報道も長く続いていました。私はぼんやりと、「これは凄いことなんだ」と思っていました。
ところが、私どもの利用者さんが、このことについて、「誰のお金が大谷選手に上がっていくのか。考えるとおかしい」と私に言ったのです。利用者さんは、生活保護を受給しながら週5日作業所に通っています。本当に頑張っている方です。
私は、「そうか」と思いました。そして、何だか自分がオメデタイ人間だと思いました。世の中のことも目も前にいる利用者さんの気持ちも何も分かっていないし、分かろうともしていなかったことに気が付きました。
これまで、大谷選手の契約金のことで、何かがおかしいというような話は、誰からも、TVからも一度も聞いたことがありません。大谷選手は天才でありかつ誰よりも努力を惜しまなかった。契約金の額の大きさは、その純粋な人間性ゆえ世界中の人から評価されている結果だと思っていました。
でも、大谷選手の報酬について、もし何もおかしくないというのなら、世界にある格差についても、また、この世界の人が味わう様々な苦しみについても何もおかしくないということになるのではないでしょうか。大谷選手の報酬と世界の苦しみは、どこかで繋がっているのではないかと思うのですが、どうでしょうか。
誰もが知っていると思いますが、お金は“下”から“上”に流れています。何かが誰かがそのようなシステムを作り上げたという訳でもなさそうですし、どうしてそのようなことが起きているのでしょうか。
利用者さんが私たちの支援を受ければ、利用者さんのお金は私たちの元に流れて来ます。そして、私がTVでメジャーリーグを観戦すれば、私のお金はメジャーリーグや大谷選手に流れていくのだと思います。単純なことですが、お金が“下”から“上”に流れることは、誰も止められないのでしょう。
しかし、どうして止められないのでしょう。地震とは違い、人間社会で起きている様々な苦しみの現象、例えば戦争もそうですが、誰も止められません。単純そうに見えて、問題は複雑なのでしょうか。
昨年来、私の周りで戦争反対を口にする人はたった2人しかいません。私はもちろん戦争反対ですが、一度もそれを口にしたことはありません。私は、私も含めて、「戦争反対」と口にしない人たちばかりと生きているのです。聞こえるのは、「停戦の合意には幾つもの大きな課題と問題がある」という知識人がTVで話すコメントだけです。
大谷選手の契約金のことが「おかしい」と言う人もいません。
私の周りでは無関心と無理解がはびこっているのでしょうか。それとも、共感する心はあっても諦めや何らかの圧力を感じて何も言えないのでしょうか。
能登で支援している人たちには、「何とかしたい」という気持ちから始まってスコップ一搔きに至るまでの人間の熱くて強靭な心の流れを感じます。
私たちは、見える悲惨見えない悲惨が溢れている本当に大変な時代を生きることになっているようです。
障害者支援の仕事は、無関心・無理解とは全く反対にある心を使う行為だと思います。一人ひとりの利用者さんに対して、何故そのように考え、喜び苦しんでいるのかを理解することから始まっていくものと思っています。
今年私は、人間としてもう一回原点に戻り、利用者さんに対してしっかり理解していくことをやっていこうと心に決めています。そして、力不足ですが、社会についても同様にしっかり理解していこうと考えています。もう一回、そこから始めます。