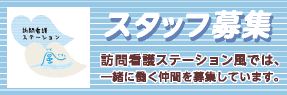私たちと一緒に「風」で訪問看護をしませんか 訪問看護ステーション風土屋秀則
新年あけましておめでとうございます。
今年も訪問看護師募集のお願いをいたします。
今年私たちは、多くなる一方の訪問看護への利用依頼に応えるため、新たに事業を開設しようと計画しております。そのために若干名の職員さんを募集しております。
私たちは、訪問看護を希望される精神障がいをお持ちの方達全員に私たちの訪問看護を提供させて頂きたいと考えております。訪問看護は、本当に様々な形でその方に合った援助を差し上げることが可能です。地域で管理されることなく自由に、また一般の市民と対等に生きる精神障がいを持つ方に、寄り添う形で支援をさせて頂くことの中には、思いもよらない多くの喜びが生まれます。
昨年私たちは1名の職員を採用したしました。しかし、その後も利用者さんは増え続け、現在すでに受け入れに無理が生じてきています。利用依頼をお断りするのは心が痛むところです。
そこで私たちは、依頼に応えるため複数名の職員さんを採用させていただき、新たにステーションを立ち上げることを考えました。そこで一緒に訪問看護の仕事をしてくださる方を探しています。少なくとも3名新職員さんが必要となっております。
精神科訪問看護のニーズは今後も高まる一方です。病院での治療技術が進めば進むほど、相対的にも社会的入院は増え、人権の問題と相まって医療経済的な理由からも精神障がいを持つ方達は地域で生活することを望まれるようになります。
私たちは、支援をさせてもらいつつ地域で共に生きるということを、病院さん始め地域諸関係機関そして非力ですが私共福祉部門とチームとして協働しながら進めています。幾分古い言葉になりましたが、「共生社会」、それを私たちは目指しています。
以前も申しましたが、これまでそんなに立派な仕事をしてこなかった方でもいいのです。経験の浅い若い方でも大丈夫です。入職後丁寧に指導をさせて頂きます。私共「風」で、専門職としても人間としても成長して頂ければいいと考えております。
私たちと夢に向かって一緒に仕事をしていきませんか。